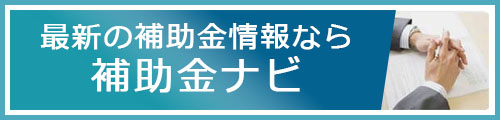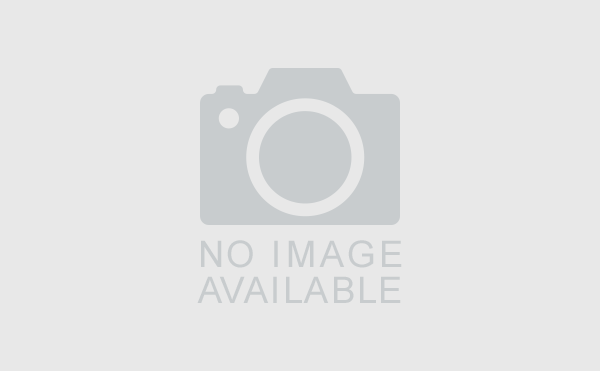「省力化投資補助金(一般型)」の第2回公募の採択発表がありました。当補助金のこれまでの採択率は以下の通りです。
○第1回公募
締切日:2025/3/31、応募件数:1,809件、採択件数:1,240件、採択率:68.5%
○第2回公募
締切日:2025/5/30、応募件数:1,160件、採択件数: 707件、採択率:60.9%
当補助金は、令和5年度の補正予算で計上され、更に事業再構築補助金基金の見直しにより当該基金の残高を加えて実施されています。令和5年度補正予算等の資料によれば、両者を加えて予算総額5000億円、令和8年度末までに新規受付及び採択を終了するとされています。
2024年度から省力化補助金(カタログ注文型)が実施され、2025年度からは、2024年度にものづくり補助金の一部として実施されていた「省力化(オーダーメイド枠)」を、省力化補助金(一般型)として追加する形で実施されています。
経産省作成のパンフレットでは、当補助金は「人手不足に悩む中小企業等に対して個別の現場や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を支援します!」とされています。
ものづくり補助金が「革新的な新製品・サービスの開発」を目的とし、省力化投資補助金(カタログ注文型)の支援対象が「カタログに掲載された汎用製品の購入」であるのに対して、省力化投資補助金(一般型)は「生産・業務プロセス等の効率化」を目的とし、「オーダーメイド設備や個別の現場に応じて組み合わせた汎用設備、システム等を導入する事業計画」を支援対象である点が、各補助金との相違であると記載されています。
尚、これまでの2回の公募による採択では、「省力化効果が高い」という点に重点がおかれ、「オーダーメイド設備」という要件は必ずしも重要視されていないようにも思われます。(筆者私見)
また、採択率は、2024年度実施ものづくり補助金「省力化(オーダーメイド枠)」が、17次、18次が、各々29.4%、34.1%であったのに対して、第2回までは前述の通り60%以上と、とても高くなっています。
では、第3回以降の採択率はどうなるでしょうか。
筆者は、「次回以降は50%程度を上限として徐々に下がって行く」と見込んでいます。
その理由は以下の通りです。
・第1回締切の採択率が、68.5%と高かったことから、応募者の増加が予想されること。
・補助金支援を業としている「補助金コンサルタント」が、高い採択率を売りに、省力化投資補助金(一般型)の活用に力を入れていること。
同一の予算内で実施される補助金は予算の制約により、採択率は後の公募回ほど低くなる傾向がありますので、当補助金についても徐々に下がって行くと考えるのが自然です。
○今後に向けての対策
採択率が下がれば、事業計画を入念にブラッシュアップすることで、採択の確率を少しでも上げることは当然ですが、その上で、当補助金については「省力化効果が高い」ことが審査において重要な点となっていますので、以下の点も考慮されることをおすすめします。
当補助金の公募要領に以下の記載があります。
省力化投資補助金(カタログ注文型)の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品について、本事業で導入する場合、省力化効果が十分に見込める設備を導入する計画であると認められるため、審査の際にも一部考慮することといたします。
ただし、製品カタログに掲載されている製品をそのまま導入するのではなく、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数、搭載する機能等が変わる場合や、省力化に資する汎用設備を複数組み合わせることでより高い省力化効果や付加価値を生み出す場合に限って、本事業の対象となることに留意してください。
但し、製品カタログに登録されている製品の数に限りがありことから、この措置を利用できる申請者は限られていました。
第3回公募から以下の審査項目が「政策面」の審査に追加されました。
・革新的で優れた省力化技術を持つ中小事業者の製品(イノベーション製品)を導入する意欲的な取組を通じて、人手不足という我が国の社会課題を解決する製品の市場拡大に寄与することが期待できるか。
※製品の革新性や製造元が中小事業者である事を示す追加資料を提出いただき、導入予定の機器装置が「イノベーション製品」に該当すると認められた企業は、審査で考慮します。
当補助金における「イノベーション製品」に該当する主な要件は、以下の通りです。
・著しく高い省力化効果が確認できること
・高い革新性のある製品であること
・中小の製造事業者が製造する製品であること
「イノベーション製品応援プログラム」については、以下のURLをご覧ください。
https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/innovation_support_program_outline.pdf
従って、製品カタログに登録のない製品導入でも、応募申請と同時に販売業者との連携により「イノベーション製品応援プログラム」へ応募し、「イノベーション製品」に該当することが認められれば、審査において考慮されますので、ぜひご検討をください。
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
中小企業庁関連の「過去の主要補助金応募採択実績」をまとめましたのでご覧ください。
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
|
リンク
|
リンク
|