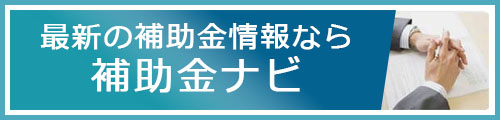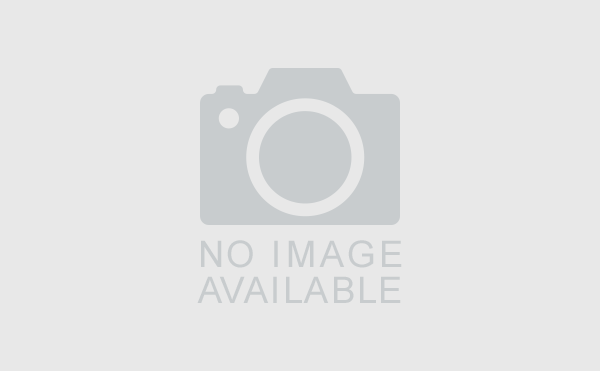この講座は、小規模事業者持続化補助金<通常枠>の申請用事業計画を、採択確率を高めつつ、スムースに策定するための方法を3回に分けてお伝えしています。今回は第3回です。
【第1回:申請用事業計画の構成と記入項目を理解しよう】はこちらから
【第2回:審査項目に適合した事業計画で採択確率をアップ!】はこちらから
【第3回:記入例の活用方法】
記入例の紹介
事業計画(経営計画、補助事業計画)の記入例が公開されています。場所がとてもわかりづらいので注意が必要です。電子申請画面にログインし、経営計画および補助事業計画の入力画面の上部の「具体的な内容については、経営計画(補助事業計画)の記入例をご確認ください。」から、リンクを辿って確認することができます。(PDFでダウンロードできます。)
記入例の記載状態は以下の通りです。
(1)とても簡潔に記載されています。
(2) 当然ですが、要件は充足し、計画審査の各項目にも適合していると考えられます。
(3) 記載量(WORD A4換算):
経営計画が、約3ページ、補助事業計画が、約1.5ページに相当し、やや少なめです。
記入例をお手本にして、同じレベルを目指すべきか
この記入例について、筆者は以下の通り考えています。
(1) 2022年公募時に公開されていた記載例(当時、事業計画は、経営計画と補助事業計画まとめてPDF形式にて提出)とほぼ同様の内容です。(一部変更箇所あり)
(2) 当時の採択率は60%台(2022/6締切:62.9%、2022/9締切:64.0%、2022/12締切:64.0%、2023/2締切:58.9%)と比較的高い採択率で推移していました。これに対して、2024年公募では30~40%台(2024/3締切:41.8%、2024/5締切:37.2%)です。
(3) この記入例が作成された当時は、現在のように「事業計画内容を申請システムに登録してから支援依頼する。」という方法ではなく、「参考書式を使って事業計画を書いたものを、相談時に持参」する方法でした。その為、商工会・商工会議所では、相談前には事業計画書の状態を把握することができず、計画とは言えないような内容も多くあったものと思われます。
そこで、「このレベル程度のものは作成してから相談して欲しい。」というものを提示したものと考えています。記入例の完璧なものに近づけ過ぎると、申請しようと考える事業者が激減する可能性もあるので、「これで十分」というレベルでは無いのではないかと思っています。
(4) 記入例のビジネスモデルは、コーヒー豆やドリップバッグ等、コーヒー関連の販売店が、店舗とオンラインショップでの販路拡大をめざすという、比較的わかり易いビジネスモデルですので、この例ではビジネスモデルの説明に行数を割く必要はありません。しかし、事業の中には、わかりづらいビジネスモデルやニッチな市場向け商品(サービス)など、事業そのものや背景等の理解のために一定の説明が必要なものも多いのではないでしょうか。また、専門用語を使用した場合には、その説明も必要となる場合もあります。そのため、文章量はある程度増えざるを得ないことも多いと考えています。
以上より、採択の確率を高めるためには、この記入例を十分に参考にしていただいた上で、審査項目を熟読し、更に上のレベルを目指した方が良いと考えます。
ブラッシュアップすべき点も考えよう
それでは具体的には、この記入例に対してどのような点をブラッシュアップすれば良いのでしょうか。ブラッシュアップのポイントをいくつかあげてみます。(あくまでも筆者の主観です。)
(1)【経営計画2-2. 顧客ニーズ】現状の事業別売上比率等の分析が主体となっているが、顧客層別の嗜好やその動向など「顧客ニーズ」の掘り下げが欲しい。
(2)【経営計画 3. 自社や自社の提供するサービスの強み・弱み】できれば、競合他社との比較を含めて、強み・弱みを記載した方が、記載内容が詳細化、具体化できる。
(3)【補助事業計画 3-1. 具体的な取組内容】この取組についての、実施日程・実施体制等が記載されていると、より具体性が増す。
(4)【補助事業計画 4-2. 効果の試算】本事業の効果として、得られる利益による投資の回収についての記載があると、より効果が明確になる。 ・・・・・など
小規模事業者持続化補助金対策セミナーのご案内
補助金ナビと提携しています「経営支援オフィスマツナガオンラインストア」が提供しています小規模事業者持続化補助金「採択確率をアップする申請書作成方法」セミナーでは、申請用事業計画の設計図を作成するためのワークシートおよび事業計画書を完成させるための「フレームワーク」等をご提供しています。
当セミナーでご提供している各種資料は、筆者自身の事業者としての多くの補助金申請や支援者としてのノウハウを活かし、審査項目との適合度を上げるためのポイントをカバーしたものになっています。
当セミナーでは、
・当補助金の審査項目等記載すべき事項を踏まえた事業計画(経営計画および補助事業計画)の「フレームワーク」
・申請用画面項目と一致した事業計画書を完成させるための「ワークシート」
・事業計画作成後の「チェックリスト」 等の資料の
「ダウンロード」によるご提供、および
・審査のポイント解説
・資料の具体的な活用により、採択確率をアップする事業計画作成方法
・採択事例紹介 等 を
「オンデマンド配信」によりお伝えする講座としてご提供しています。ぜひご活用ください。
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
また、記事内容には筆者の個人的な見解が多く含まれています。
補助金の応募等に際しては、公募要領等をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
|
リンク
|
リンク
|